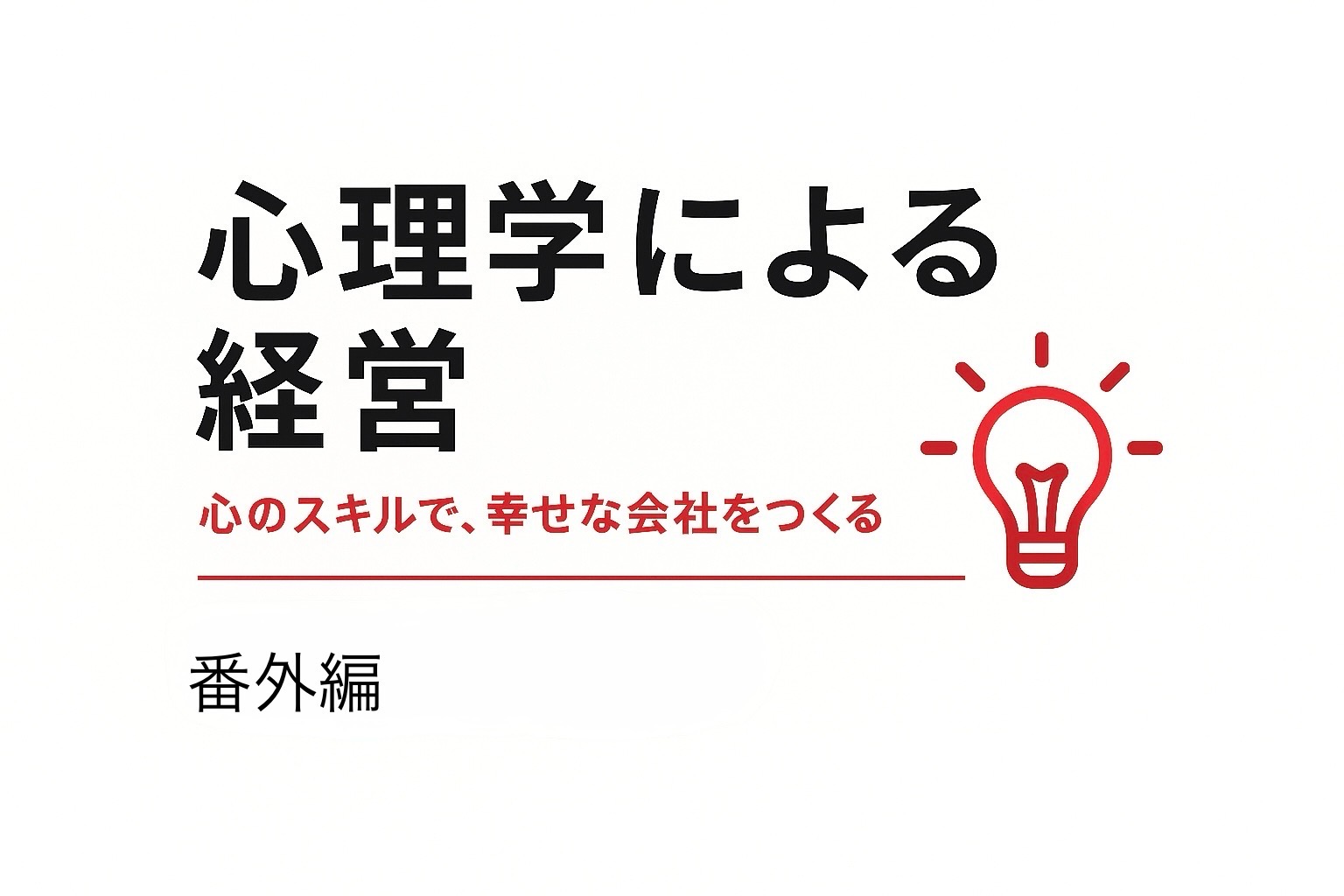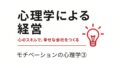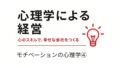「成果」と「心」を統合する、新たな経営の視点
「マネジメントの父」と呼ばれるピーター・ドラッカー。その提唱したマネジメント論は、20世紀後半から現在に至るまで、経営のスタンダードとして世界中の企業に浸透してきました。組織の成果を最大化するための体系だった理論は、多くの経営者にとっての羅針盤となってきたのです。
一方で、私がこの連載で提唱している「心理学による経営」は、人の“心の動き”に焦点を当て、社員一人ひとりの内発的なモチベーションを高めることを出発点としています。このアプローチは、一見するとドラッカーの理論と相反するもののように思えるかもしれません。
しかし結論から言えば、両者は対立ではなく、むしろ相互補完の関係にあると私は考えています。
ドラッカーが築いた強固な経営の「骨格」に、心理学が「血と肉」、つまり人間性という生命を吹き込む。それこそが、私の目指す「幸せな会社」のあり方です。
ドラッカーが描いた「成果を出す組織」の設計図
ドラッカーのマネジメントは、企業が社会的な目的を果たし、成果を生み出すことを最重要視します。そのための手段として、目標設定、組織構造、権限委譲、責任、そして知識労働者の生産性向上といった、マネジメントの普遍的な原則を確立しました。
彼は人を「最も重要な資源」として扱い、その力を最大限に発揮させるにはどうするか、徹底的に考え抜いています。
つまりドラッカーは、組織という「器(うつわ)」をどう設計するか、その骨格を緻密に構築したのです。
同時に、彼の著作には「人間は目的を持ち、学び、成長する存在である」という認識が何度も表れています。人間の尊厳を重んじ、自律性を尊重する姿勢も随所に見られ、そこには単なる効率主義ではない、深い人間観が流れています。
「心理学による経営」が吹き込む、組織の“内なる生命力”
一方で、「心理学による経営」は、その「器」の中で働く人々の内側に注目します。人が心からやりがいを感じ、創造性を発揮し、自ら動き出すにはどうすればよいのか。その答えを、心理学や哲学の知見から探っていくアプローチです。
たとえば、マズローの欲求階層説における「承認」「自己実現」などの高次の欲求や、自己決定理論が示す「自律性」「有能感」「関係性」といった内発的動機づけの条件──これらは、ドラッカーが組織の枠組みを作る一方で、その中の人間をどう活かすかという視点を強く補完します。
心理学によって組織は、「やらされ感」に満ちた場所から、ワクワクしながら貢献できる空間へと進化するのです。
| 項目 | ドラッカーのマネジメント | 心理学による経営 |
| 主な関心 | 組織の成果、目的の達成 | 人の心の充足、内発的動機づけ |
| アプローチ | 経営の構造化(MBO、組織設計など) | 心理学・哲学を通じた人間理解と動機づけ |
| 重視するもの | 効率性・責任・権限 | 自律性・有能感・関係性 |
| 視点 | 外部構造(仕組み、役割、成果) | 内部構造(感情、動機、つながり) |
| 関係性 | 組織の中での役割理解と成果貢献 | チーム内の共感と信頼、ワクワク感の創出 |
補完し合う、二つの視点
このように見ると、ドラッカーと心理学はアプローチが異なるだけで、本質的には同じ目的を目指しています。
自律性の尊重
ドラッカーは、知識労働者には自律性が不可欠だと説きました。心理学は、それが「動機づけの根源」であることを、科学的に証明しています。
目標とフィードバック
ドラッカーのMBO(目標による管理)は、明確な目標と定期的なフィードバックを重視しました。これは、チクセントミハイの「フロー理論」が説く「明確な目標と即時のフィードバック」と重なります。
人間関係の重要性
ドラッカーは組織構造の合理性を追求しましたが、心理学は「つながり」や「認められたい」という関係性の欲求が、チームの結束力や生産性に不可欠であることを示します。
両者は、「設計」と「動力」、「骨格」と「血肉」のような関係にあると考えられます。
成果と心の統合──「人間性ある経営」の時代へ
ドラッカーのマネジメントは、企業が社会の中で価値を生み続けるための堅牢な土台を提供しました。
しかし、その土台の上で働く人々の心が「やらされ感」に囚われていたり、真の充足感を得られなかったりするなら、組織は本来持つ生命力を最大限に発揮できません。
「心理学による経営」は、この構造に“人がいきいきと働く仕組み”を加えることで、成果を出しながらも人間性を失わない──むしろ人間性があるからこそ成果が出る、という新たな組織像を描き出そうとしています。
私たちは今、経済合理性やルール偏重の時代を越え、「人の心」に立脚した経営に舵を切るタイミングに来ています。
ドラッカーの知恵と心理学の真理。その両輪がかみ合ったときにこそ、「ワクワクチームワーク」が息づく、真に幸せな会社が生まれるのです。