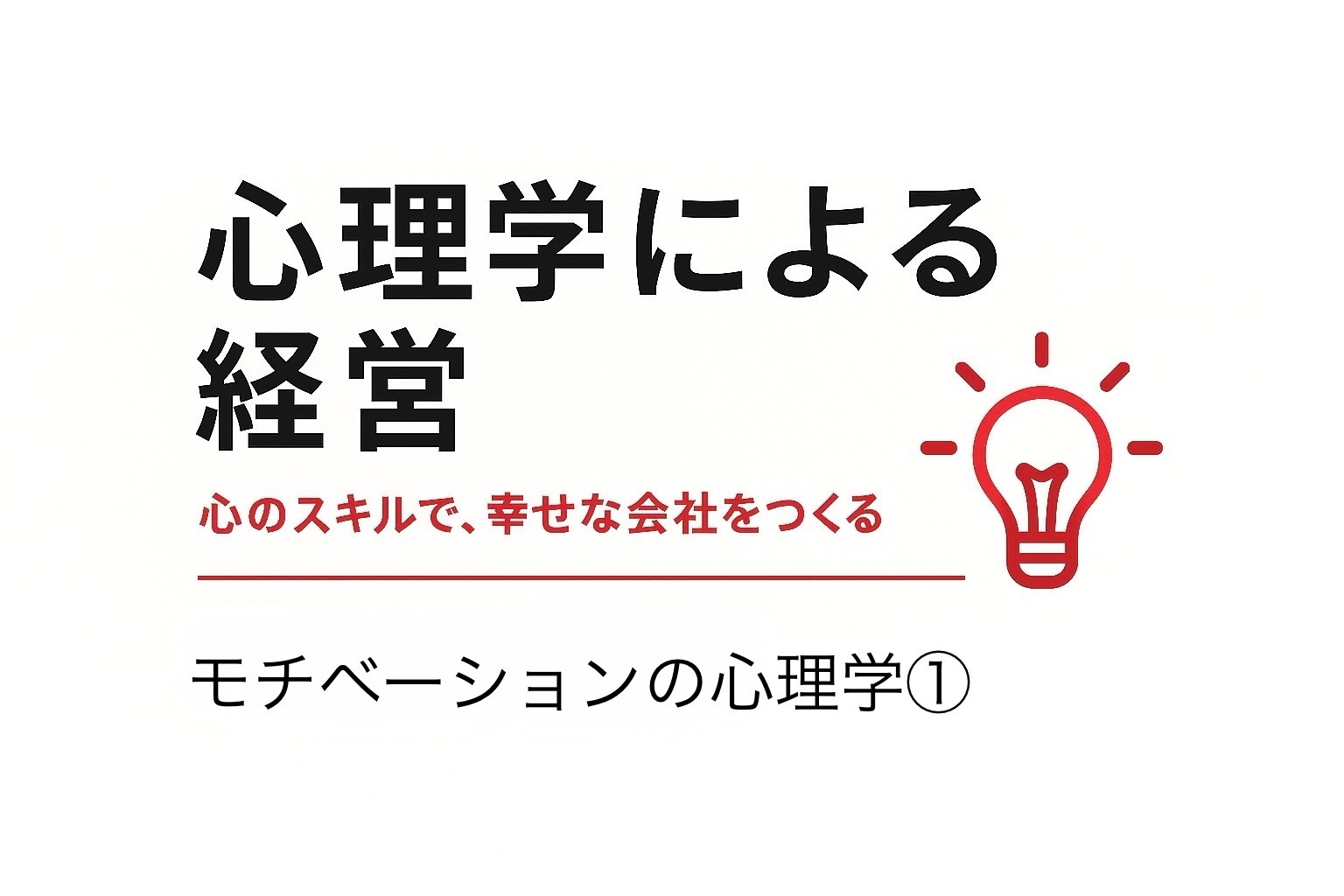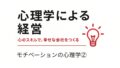「お金」だけでは人は動かない ― 欲求の階層から考える“やる気”の本質
給料を上げたのに
政府が企業に対して「賃上げ」を要請するようになってから久しくなります。物価高騰が続く中で、家計の実質購買力を高め、景気を回復させたいーーその目的は明確で、多くの企業もその動きに応じて給与や賞与を見直すようになってきました。
しかし、現場にいる経営者やマネージャーからはこんな声も聞こえてきます。
「給料を上げたのに、思ったほど現場の活気が戻らない」
「制度を整えたのに、社員が自主的に動かない」
当の社員からは、
「物価防衛できていない」
「他所はもっと上がっているようだ」
などと、あまり満足の声は聞こえてきません。
これは、単なる感覚ではありません。実際、「お金で人は動く」という前提は、どこかで崩れてきていることを示唆しています。
ビジネスシーンにおいては、「売上」「利益」といった目に見える「数字」で物事が語られることが圧倒的に多いですよね。会社の永続性には「お金のスキル」が不可欠だと、元銀行員である私自身、経営において数字を深く読み解くことの重要性を説いてきました。しかし、どれほど緻密な数字の管理を行い、魅力的な報酬体系を整備しても、なぜか社員のモチベーションが上がらない、チームに活気がない、というのが多くの職場で起こっていることではないでしょうか?
私たちは、経済学的な視点や法的なルール、ガバナンスといった「縛り」の中で、ともすれば「人」という最も大切な要素を見失いがちです。特に、果てしない利潤追求という資本主義の論理が前面に出る現代において、組織で働く人々は時に窮屈さや閉塞感を感じています。
「もっと給料を上げれば、もっと頑張ってくれるはずだ」「ルールを厳しくすれば、不正はなくなる」ーーそうした考え方は一見合理的ですが、本当に人の心を動かし、持続的な成長を促す本質なのでしょうか?
「欲求」には階層がある
ここで、一度立ち止まって考えてみたいのは、私たち人間が持つ「欲求」の普遍性です。経営戦略や組織のルールは時代や状況によって変化するものですが、人間の根源的な欲求は、有史以来ほとんど変わっていません。心理学や哲学が教えてくれるのは、まさにこの「変わらない真実」です。それは、流行に左右されることのない、人間性を取り戻すための「リベラルアーツ」であり、私たちが目指す「心のスキル」の絶対的な正義の源泉なのです。
人が自ら動き出す「心のスイッチ」を知る上で、最も基本的な、そして普遍的な示唆を与えてくれるのが、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求の階層説」です。
この連載においても、マズローの理論はすべての土台になります。だからこそ、改めて丁寧に触れておきたいのです。
「欲求」は高みを目指す
マズローは、人間の欲求を5つの階層に分け、下位の欲求がある程度満たされてから、上位の欲求を追い求めるという構造を提唱しました。
1. 生理的欲求(Physiological Needs)
食事、睡眠、排泄といった生命維持に関わる基本的な欲求です。
会社でいえば、適切な給与、安全な職場環境などがこれに当たります。これが満たされなければ、人は働くことすら難しくなります。
2. 安全の欲求(Safety Needs)
身体的・精神的な安全、安定した生活を求める欲求です。
雇用の安定、福利厚生、ハラスメントのない環境などが該当します。ここが揺らぐと、人は不安を抱え、本来の力を発揮できません。
3. 社会的欲求(Belongingness and Love Needs)
人とつながり、所属していると感じたいという欲求です。
チームワークや仲間意識、「ここに自分の居場所がある」と思えることは、働く上で大きな安心感と活力につながります。
4. 承認欲求(Esteem Needs)
他者から認められたい、自分の存在や貢献に価値を感じたいという欲求です。
正当に評価されること、責任を持てるポジションにいること、成果をフィードバックされることが、モチベーションの源泉となります。
5. 自己実現欲求(Self-Actualization Needs)
自分らしく生きたい、自分の可能性を最大限に発揮したいという、最も高次な欲求です。
仕事を通じて創造性を発揮したい、新たな挑戦がしたい、自分の内面と外の世界を結びつけて働きたいーーそうした思いの集積です。
「お金」では満たされない
ここで重要なのは、お金や物質的な報酬が満たせるのは、主に「生理的欲求」や「安全の欲求」といった低次の欲求であるという点です。もちろん、これらは働く上での「幸福の物質的基盤」であり、不可欠な土台です。しかし、どれほど高額な報酬を与えても、社員が「孤独」を感じていたり、自分の仕事が誰にも「承認」されないと感じていたり、あるいは「成長の機会」が見出せなかったりすれば、彼らのモチベーションはすぐに頭打ちになってしまいます。
逆にいえば、お金や制度が整っていても、それだけでは「心の中の渇き」は癒されないのです。だからこそ、賃上げをしても、社員が必ずしも自発的に動くようになるとは限らないのです。
私は、幸せな会社とは「ワクワクチームワーク」が根づいている組織だと考えています。そこでは、単に生活のために働くのではなく、仲間とのつながりや自分の成長に喜びを感じながら働くことができます。
多くの企業は、低次の欲求を満たすこと(例えば、給与水準や安定した雇用)には注力していますが、その先の「つながりとしての幸福」や「自己実現としての幸福」といった高次の欲求を満たすためのアプローチが不足しがちであると私はみています。これが、「お金だけでは人は動かない」「人の心はお金で買えない」という、多くの経営者が直面する現実の核心なのです。
経営に必要なのは「心のスキル」
マズローの欲求階層説は、時代や文化、産業の違いを超えて、私たち人間の心の普遍的な動きを示しています。この普遍的な欲求に寄り添い、高次の欲求を満たすことこそが、真に社員を動機づけ、組織全体に「ワクワクするチームワーク」を生み出す鍵となります。
会社は、「生理的・安全欲求」だけでなく、「社会的・承認・自己実現欲求」までを包み込むような場であるべきです。それが、人のモチベーションを根本から支えるということです。
そこで必要となるのが「心のスキル」です。それは、心理テクニックで人を操ることではありません。社員一人ひとりの内面に耳を傾け、「この人はいま、どの段階の欲求に苦しんでいるのか?」を感じ取る力です。
部下のやる気が出ないとき、それは単に本人の問題ではなく、上位の欲求が満たされていないという“サイン”かもしれません。そのサインに気づき、働きかけられるのが、本当のマネジメントです。
そしてこれは、大企業に資本力や組織の規模で劣る中小企業にとって、むしろチャンスだと私は思っています。
この連載では今後、フロー体験や心理的安全性、承認欲求、共同体感覚など、さまざまな心理学・哲学の理論を扱っていきます。ただし、すべての理論には、人の欲求には段階があり、それぞれに応える必要があるというマズローの知見が通底しています。だからこそ、マズローの欲求階層説は「古典」でありながら、これからの経営の「新しい出発点」でもあるのです。
次回予告
次回は、社員が「やらされている」感覚から抜け出し、自分の内側から動き出す力を支える理論ーー自己決定理論(デシ&ライアン)を取り上げます。
「自分の意志でやりたい」と感じたとき、人はどう変わるのか?
その答えを、一緒に探っていきましょう。