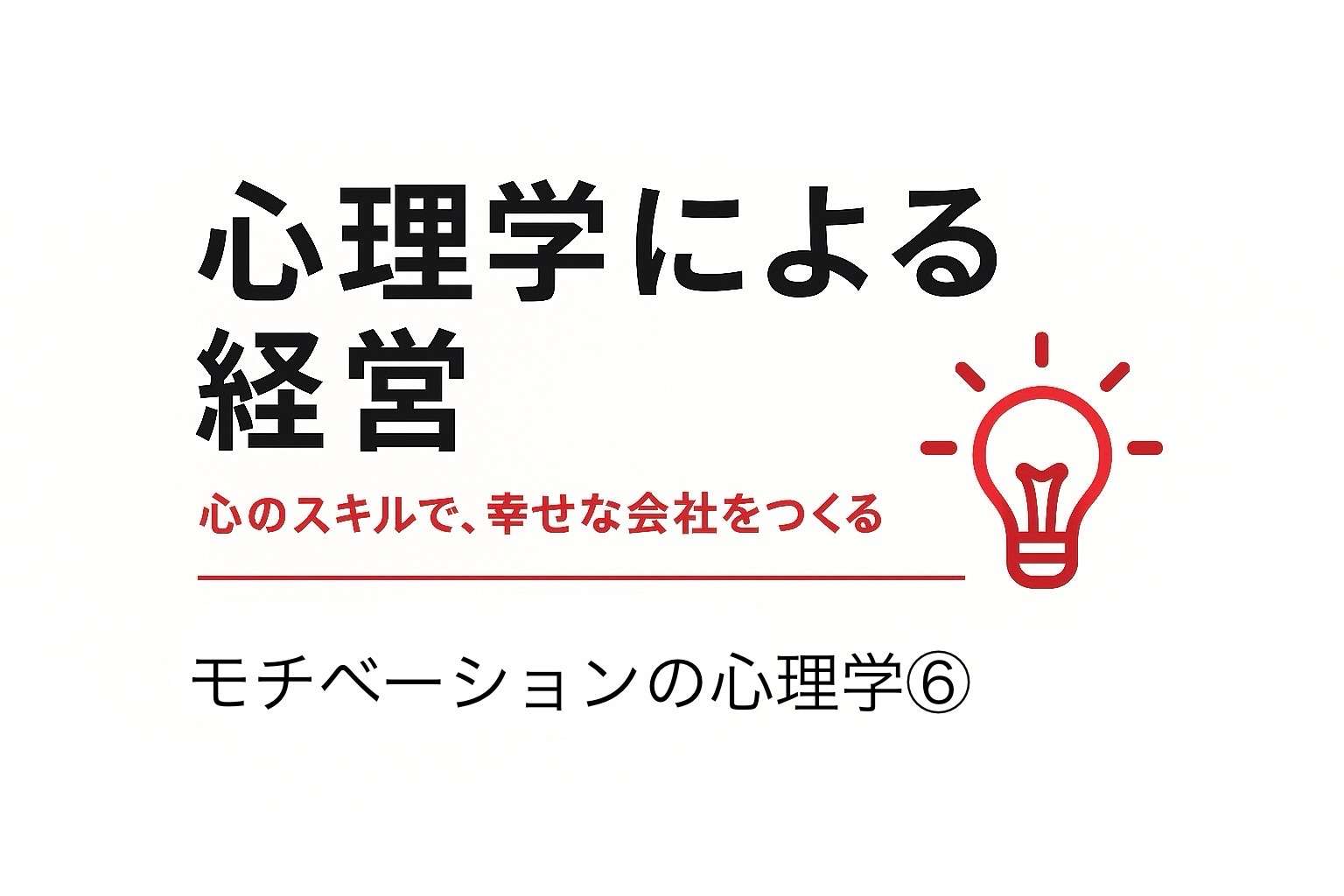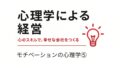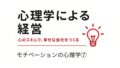「不公平感」がやる気を奪う── 心の中のバランスシートとどう向き合うか
あなたは、こんな光景に心当たりはありませんか?
「同期のAさんの方が、自分より残業も少ないのに、なぜか評価が高い」
「後輩のB君は、明らかに成果を出していないのに、給料は自分と変わらない」
私が現役時代に、マネジャーとして常に悩まされ続けたのが、このように「他者と比べて自分が損をしているのではないか」と不平不満を抱えるメンバーの存在です。いえ、私自身も他者との比較において不満を抱え続けた張本人と言えるでしょう。
こんなことなら、評価制度なんてない方がマシだと思うことさえありました。
たとえ自分の仕事には満足していても、「不公平だ」と感じた瞬間、人は驚くほど簡単にやる気を失い、最悪の場合、組織への信頼さえ揺らいでしまいます。
なぜ、私たちはこれほどまでに「不公平感」に弱いのでしょうか?
人は無意識に「比べている」── 公平理論のメカニズム
この心理の背景を解き明かしたのが、心理学者のJ.S.アダムスが提唱した「公平理論(Equity Theory)」です。
この理論は、人のモチベーションが、自分の努力や成果を、他者のそれと比較することで決まると説明しています。
公平理論の核心は、人間が常に「投入(Input)」と、そこから得られる「結果(Outcome)」のバランスを無意識に測り、それを他者と比較している、という考え方です。
投入(Input):仕事に費やした努力、時間、スキル、経験、熱意など
結果(Outcome):仕事から得られた報酬、給与、昇進、承認、やりがいなど
人は、「自分の投入:自分の結果」の比率が、「他者の投入:他者の結果」の比率と等しい時に、公正だと感じ、モチベーションが維持されます。しかし、この比率が崩れると、「不公平感」という心理的な不快感が生まれます。

たとえば、自分が「これだけ頑張っているのに、あの人と同じ評価なのは納得できない」と感じるのは、投入と結果のバランスが他人と釣り合っていないという心理的ストレスが生まれている状態です。
この不快感を解消するために、人は自然と「帳尻合わせ」の行動を始めます。
帳尻合わせが始まるとき── 行動のパターン
過小評価されていると感じると
- 自分の投入を減らす:「どうせ頑張っても報われないなら……」と、仕事の手を抜く。
- 自分の結果を増やそうとする:上司に不満をぶつけたり、昇給や異動を要求したりする。転職を考える。
過大評価されていると感じると
- 自分の投入を増やす:「給料をもらいすぎているから、もっと頑張らなきゃ」と過剰に働く。
- 結果(報酬)の価値を下げる:「この仕事は、ハードで嫌なものだから、これくらいの報酬が妥当なのだ」と正当化する。
これらの行動がもたらすのは、モチベーションの低下や燃え尽き、さらには組織全体の空気の悪化です。
公平理論は、報酬や評価の「絶対的な額」よりも、「相対的なバランス」が人の心に大きな影響を与えることを教えてくれます。
公平理論の落とし穴──「理屈」では解決しない
アダムスは、不公平感を解消する理論上の解決策として以下を提示しています。
- 投入を変える
- 結果を変える
- 比較対象を変えるために、投入・結果・比較対象を変える
たとえば、多くの職場で「360度評価」の導入や「評価基準の見直し」など、マネジャーの評価にメスを入れることで「制度による公正性の担保」が試みられています。
しかし私の実感としては、こうした施策が現場の不公平感を根本から解消することはほとんどありません。むしろ、煩雑な手続きを増やし、管理職を「誰もやりたがらない罰ゲーム」へと変えてしまう一因になっていると、私は感じています。
なぜなら、不公平感の正体は、「制度の不備」ではなく、本人の自己評価と、他者(上司や組織)の評価とのズレにあるからです。
人は、努力や熱意といった主観的な「目に見えない投入」に、無意識のうちに大きな価値を置いています。一方で、会社は客観的な数値や目標達成などの「見える結果」に基づいて評価せざるを得ません。
このズレが存在する限り、そして他者との比較という相対的なバランスにこだわり続ける限り、全員が満足する「完璧な評価」にたどり着くことは、残念ながらあり得ません。
このズレを「どっちが正しいか」という議論に持ち込むと、水掛け論となり、不満はさらに増幅してしまいます。
過去ではなく、未来志向で「満たされる状態」を探す
では、どうすればこの不満を建設的な方向に変えることができるのでしょうか。
私が推奨するのは、他者との比較から離れ、「未来志向」で満たされる状態を一緒に探すアプローチです。
Step 1:不満の奥にある「本音」に耳を傾ける
不満を述べる人の言葉の裏にあるのは、「自分は何に価値を置いているか」という、その人なりの大切な思いです。これを丁寧に引き出すことが第一歩です。
Step 2:「どうなれば満たされるか?」を問う
過去の評価の正当化ではなく、未来志向の問いかけにシフトします。
「どうなれば、あなたはもっと満たされるだろう?」
「そのために、何があればいいだろう?」
たとえば、「もっと裁量を持って働きたい」という声があれば、「そのためには何を身につければよいか?」を一緒に考え、行動に落とし込むことができます。
「評価される存在」から「自分のキャリアの当事者」へ
このアプローチは、組織の評価制度にただ従うだけの存在から、自分自身の価値を見出し、未来を切り開く当事者へとメンバーを変えていく力を持ちます。
これは、自己決定理論や次回扱う自己効力感とも通じる、深いマネジメントの視点です。
「公正さ」は制度ではなく、心のスキルで築く
公平理論は、「人はなぜ比較してしまうのか」「不満はどこから生まれるのか」という、非常に人間らしい感情を理解するうえで有効な理論です。
しかし、それを解決へと導くのは、マニュアルでも制度でもなく、「心のスキル」です。
メンバー一人ひとりの心に寄り添い、その人が本当に「満たされる状態」を、過去の評価ではなく、共に未来へのステップを描いていく。
それが、公正さという組織の土台を築き、持続的なモチベーションを支える真のアプローチだと、私は考えています。
次回は、「自分はできる」という信念が人の行動をどう変えるのか──自己効力感(バンデューラ)の視点から、成長する組織の鍵を探ります。