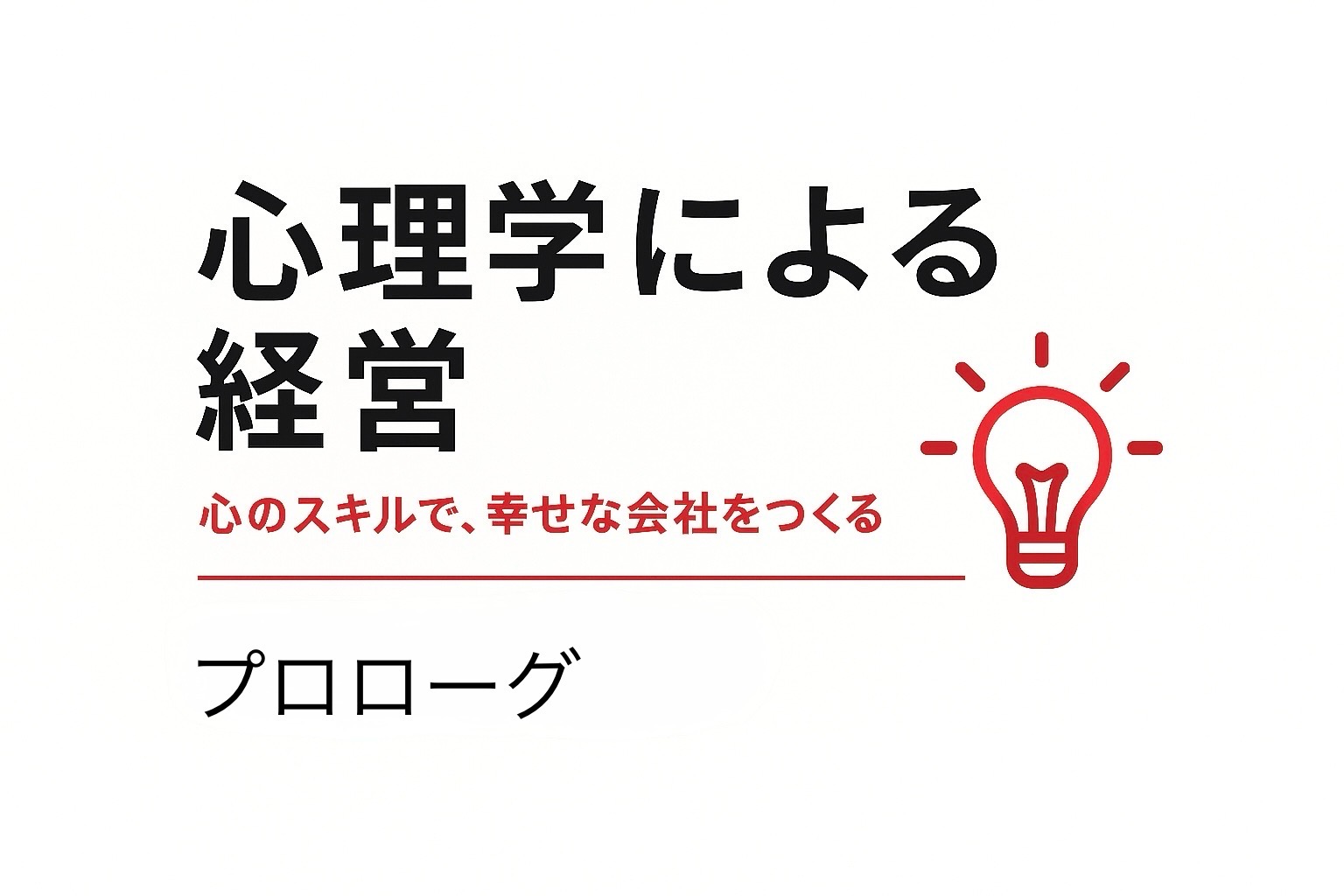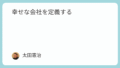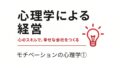前回の記事で、私は「ワクワクチームワーク」を実現するために、「つながりとしての幸福」と「自己実現としての幸福」をどう叶えるかを課題として提示しました。そしてその鍵が、私の第二の軸足である心理学的アプローチによるマネジメント、すなわち“心のスキル”にあることを述べました。
試行錯誤のなかで得た実践と、先人の知見とを重ね合わせながら、多くの示唆が得られることが見えてきた今、ようやく構想がまとまりました。ここから、「心理学による経営」というタイトルで連載を始めたいと思います。 その目的は明確です。「心のスキルで、幸せな会社をつくる」ことです。
なぜ心理学なのか
現代社会、特に組織で働く人々は、時に大きな重圧を感じています。 経済学的な数字や、厳格な法的なルール、あるいはガバナンスといった枠組みは、企業活動の効率や健全性を保つうえで確かに重要です。しかし、それらが過度に優先され、果てしない利潤追求という資本主義の論理が前面に出るにつれて、私たちは窮屈さや閉塞感を感じるようになりました。 本来、人間的な活動であるはずの仕事が、いつしか数字やルールに縛られ、人々の心が置き去りにされているのではないかと感じることも少なくありません。
さまざまな経営戦略や組織の制度は、特定の時代や会社には適するかもしれません。 しかし、それらの多くは、時代や環境の変化とともにその有効性を失っていきます。一時的な流行にすぎず、やがて限界に直面するものも多いのです。
その点で、私がここで深く掘り下げていこうとする心理学や哲学の知見は、人間という存在の根源に触れるものです。 だからこそ、時代を超えて変わらぬ真理として、組織の根底を支える力になり得ると考えています。
そして、私が目指す「幸せな会社」の姿をひと言で表したのが、ワクワクチームワークです。
- 朝、出社した瞬間に「今日もこのチームと働けるのが楽しみだ」と思える
- 自分の意見を安心して言える
- 相談したら誰かがちゃんと聴いてくれる
- 仲間の喜びを、素直に一緒に喜べる
- 自分の成長が、仲間の成長と重なる実感がある
そんなチームでは、命令や管理がなくても、人は自ら動き出します。 そしてその状態こそが、最も強く、最も持続可能な組織なのです。
心のスキルとは「相手の心を感じ取る力」
この連載のキーワードとなる「心のスキル」とは、心理学的なテクニックで人を操作する力ではありません。私が考える「心のスキル」とは、「相手の心を感じ取る力」です。それは、言葉の裏にある感情に気づく力、沈黙の中にある不安を察する力、 そして表には出ていない「本当の動機」や「声にならない欲求」に、静かに耳を澄ませる力です。この力を一言で表せば「共感」かもしれません。 ただし、ここで言う共感とは、単なる同情や優しさではありません。 人間の心の動きに目を向け、丁寧に観察し、自分自身の反応も冷静に見つめる感受性。 そして、相手の思いを“理解しよう”とする姿勢です。
多くのマネジメント論が「どうすれば人が動くのか?」という問いから出発します。 けれど私は、「その人はいま、どこにいるのか」「何を感じているのか」にまず心を寄せるべきだと考えています。人を動かすのではなく、人が自ら動きたくなる空間をつくること。 そのための基礎となるのが、心のスキルです。
これは、決して一朝一夕に身につくものではありません。 しかし、日々の対話や観察、反省と内省の積み重ねの中で、誰にでも育てていける力です。この力を発揮できる職場では、不思議なことが起こります。
- 会議でメンバーが自然に意見を出し合うようになる
- 上司が何も言わなくても、部下が「今やるべきこと」を自ら見つけて動き出す
- 問題が起きた時に責任の押し付け合いではなく、支え合いが生まれる
人は、管理されて動くよりも、「わかってもらえている」と感じたときに、より大きな力を発揮するのです。 いくら制度や仕組みを整えても、それだけでは人の心までは動かせません。 しかし、心のスキルがあるだけで、多少の不備や混沌すら乗り越えていけるのです。
現場の経験 × 心理学・哲学の知恵
私は心理学者でも哲学者でもありません。 けれど、現場での数えきれない経験の中で、「これは大事だ」と直感的に掴んできたことの多くが、 実は心理学や哲学の理論で説明できることに、たびたびそ遭遇すると同時に得心してきました。つまり私は、理論を学んで現場に応用したのではなく、現場での感性を、理論があとから裏打ちしてくれたのです。
この連載では、そんな体験をベースに、一つひとつの気づきやマネジメントのエピソードを、心理学・哲学の知見と重ね合わせながら丁寧に言葉にしていきます。
モチベーション、組織、関係性、リーダーシップ、経営戦略、そしてお金と意思決定。 多岐にわたるテーマを通じて、「心のスキル」を実践的に探求していくつもりです。
リベラルアーツとしての 「心のスキル」
私はこの「心のスキル」を、経営におけるリベラルアーツだと位置づけています。それは、数字やルールという閉塞的な枠組みから人々を解放し、 会社という場に、人間らしさや思いやり、創造性を取り戻すための知恵です。古代ギリシャで「自由人にふさわしい教養」とされたリベラルアーツは、 現代においては「自由な発想と人間的な判断を可能にする知の基盤」と言えるでしょう。心のスキルは、まさにそれにあたります。
そしてこのスキルは、経営者やマネジャーだけのものではありません。職位や肩書きに関係なく、組織で働くすべての人にとって必要な、共通言語なのです。「感じる力」を持った人が職場にひとりでも増えることで、 空気は変わり、関係性は変わり、組織は少しずつ変わっていきます。
「心のスキル」は、全員が身につけるべき力
組織にいると、陰で経営者や上司に対する不平不満を耳にすることは少なくありません。私もそういうことを言っていた一人であり、言われていた一人でもあったでしょう。確かに、心のスキルが決定的に欠如したリーダーの存在は、組織を停滞させます。 管理職や経営者にこそ、対話や共感、信頼を生む力が求められることは言うまでもありません。しかし一方で、それだけでは組織は変わらないというのもまた現実です。
- マネジャーが丁寧な1on1やフィードバックに取り組む
- 組織開発の研修を重ね、経営層が意識を変えようとする
- 制度や風土改革も実施されている
それでも、まったく組織が動かない。なぜか?
その理由は明白です。受け取る側であるメンバーの意識が変わっていないからです。心理的安全性の高い場をつくっても、誰も発言しなければ何も始まらない。エンゲージメントの向上を図っても、「どうせ何も変わらない」と冷笑している人ばかりでは意味がない。つまり、経営者やマネジャーの努力だけでは、組織は変わらないのです。
最近では、社員のエンゲージメント低下や離職率の上昇を、「上司のマネジメント不足」と結びつける論調も見られます。 もちろん、それが的を射ている場合もあるでしょう。心のスキルが著しく欠けたリーダーは確かに存在します。しかし一方で、「自分の不満をすべて上司や会社のせいにする」という姿勢が、結果としてマネジャーを“罰ゲームのような立場”に追い込み、疲弊させている現実も無視できません。すべてを「上司のせい」にしてしまう構図には、私は強い違和感を覚えます。
「自分が変わらないのは、上司がダメだから」
「自分の不満は、会社の仕組みが悪いから」
こうした思考が強くなると、責任は常に“誰か”に押しつけられます。 加えて、ワークライフバランスの浸透に伴い、定時退社のメンバーがやり残した仕事を残業代のつかない管理監督者が尻拭いするという歪んだ実態もあります。結果として、マネジャーが“罰ゲーム”のような役割を背負わされ、疲弊していくのです。さらに一部のマネジャーは、ハラスメントを意識し過ぎるばかりに部下の指導に悩み続け、組織がうまく回らない責任を一身に背負い、もう「無理ゲーだ」と感じているのです。
この連載で言う「心のスキル」は、「相手の心を感じ取る力」です。それは、人の話を丁寧に聴く力、相手の立場に立つ想像力、場の空気を感じ取る感受性です。これらは、経営者やマネジャーだけに必要なものではありません。職位に関係なく、すべての組織人にとって不可欠な力です。
なぜなら、チームは「全員」で成り立っているからです。上司がどれだけ意識を変えても、メンバーが変わらなければ組織は変わりません。逆に、メンバーの誰かが一歩踏み出せば、組織全体が変わることもあります。
心を傷つけるのは、攻撃よりも「無関心」かもしれない
ここで重要な補足をしたいと思います。
心のスキルがないというのは、なにも怒鳴ったり責めたりする人だけを指すのではありません。
- 話しかけても、まるで透明人間のように扱われる
- 相談しても、心のこもらない「そうですか」で終わる
- 喜びや悩みを共有できず、どこか空虚なやりとりしかない
これらもまた、人の心を深く傷つけるものです。
表面的には「優しくて穏やかな職場」に見えるのに、なぜか辞める人が絶えない——そうした“ホワイトすぎる”職場の背景に、実はこうした感情的な不在=エモーショナル・ディスコネクトがある場合が少なくありません。
心理学者スティーブン・ポージェスの「ポリヴェーガル理論」では、 人間の神経系は無意識のうちに「この場は安全か?」をスキャンしているといいます。誰かの表情、声のトーン、反応の質。そうした“微細な違和感”を、身体は正確に察知しています。
- 安心できるとき、私たちは社会的交流モードに入る
- 不安や孤独を感じると、戦う・逃げるモード(交感神経)か、切断・フリーズモード(背側迷走神経)になる
つまり、「声をかけても反応がない」「共感がない」といった状態は、 神経系レベルで「ここは安心できない場」と認識されるのです。
我慢せず、逃げてもいい
だから私はこれだけはお伝えしておきたい。
「無理に我慢し続ける必要はない」
いくら“ホワイト企業”と呼ばれても、あなたの心や身体が「この場は合わない」と感じているのなら、逃げることは、自己防衛であり、あなたの心を守る選択なのです。人の心をまったく理解しようとしない経営者やマネジャーに出会ってしまったとき。その場にとどまって、自分の心をすり減らしながら耐え続ける必要はありません。むしろ、逃げる勇気のほうが大切です。
それは甘えではなく、あなた自身の「心を守るスキル」なのですから。
今は、人手不足の時代です。雇ってもらう側の立場だった過去とは異なり、「自分が幸せを感じられる職場」を選ぶ時代です。心のスキルを持った上司、仲間、職場に出会える可能性は確実にあります。
- 人間関係に安心感がある
- 信頼が土台にある
- 働く目的や成長の実感がある
そうした職場でなら、気持ちよく働くことができます。
結びに
「上司が悪い」「会社が悪い」で終わらせてしまえば、そこで思考は止まってしまいます。 けれど、「自分はどう関われるだろう」と問い直すことで、組織に新しい風が吹くこともあります。心のスキルは、誰かのためにだけあるのではない。あなた自身の幸せのために必要なものなのです。
「心のスキル」を持った人が職場にひとりでも増えることで、 空気は変わり、関係性は変わり、組織は少しずつ変わっていきます。この連載が、あなた自身の「働き方」や「組織の在り方」を見直すきっかけになれば、何より嬉しく思います。
あなたの職場では、どんな心の風景が広がっているでしょうか?
次回から、その答えを一緒に探っていきましょう。