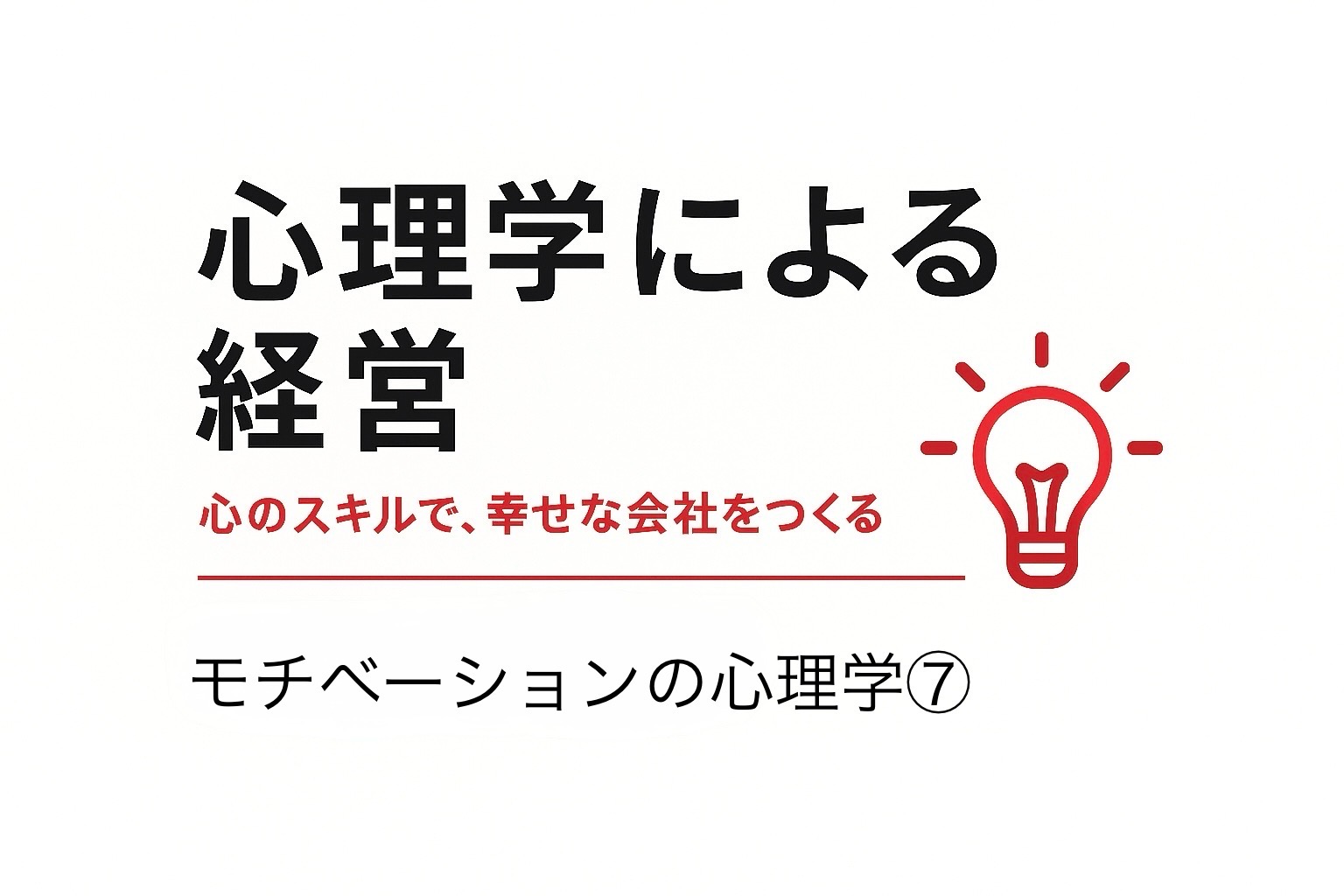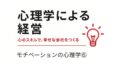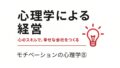「自分ならできる!」という心の力が、成長を加速させる
「伴走型リーダー」の時代?
私が銀行員の駆け出しだった頃、一つのお取引先をベテランの先輩と二人で担当していました。最初はわからないことばかりでしたが、すぐ隣で先輩の商談を見られることが心強く、安心して学べたのをよく覚えています。わからないことはその場で質問でき、振る舞いを真似しながら徐々に自分でもできるようになっていきました。今振り返っても、非常にありがたい経験です。
しかしその後、人材不足や業務効率化の流れの中で、若手が最初から一人で担当を任されるケースが増えてきました。すると、隣で手本を示してくれる存在はいません。現場に立たされた若手は「本当に自分にできるのだろうか」と不安になり、最初の一歩を踏み出すことすらためらってしまうことがあります。
そんな時代背景もあって、部下に寄り添い、支え、安心感を与える「伴走型リーダー」が求められています。それは私も大賛成であり、実際に私がマネジャーとして伴走型を実践できていた時、最もチームが活性化していたと感じています。
しかし、ここに一つの落とし穴があります。伴走しているつもりが、実は逆効果になっているケースが少なくないのです。
間違った「伴走」がもたらすもの
口出しが多すぎるリーダー
部下がやろうとするたびに細かく指示を出す。
結果、部下は「結局、自分ではできない」と感じ、自信を失っていきます。
先回りして答えを出してしまうリーダー
問題が起きる前に助け舟を出し、すぐに答えを教える。
すると部下は「自分で考える必要がない」と思うようになり、挑戦する力が育ちません。
根拠のない励ましを繰り返すリーダー
「大丈夫!やればできる!」と繰り返すが、具体的な根拠やサポートがない。
むしろ「そんな簡単に言われても…」と部下を追い詰めてしまいます。
これらはすべて「部下を支えたい」という善意から出る行動です。しかし、その結果として部下の心には 「自分には無理だ」 という思いが残り、行動意欲を奪ってしまいます。これでは、いくら伴走していても逆効果です。
では、人が「自分ならできる」と思えるように支援するにはどうすればよいのでしょうか。
ここで役立つのが心理学者アルバート・バンデューラの提唱した「自己効力感(Self-Efficacy)」という考え方です。
自己効力感とは何か
自己効力感とは、「自分は、ある行動を成功裏に実行できる」という自己の能力に対する確信のことです。
単なる楽観主義や性格的な自信ではなく、特定の状況や行動において「自分ならできる」と感じる心の力です。
たとえば、新しい顧客との商談を前にして、ある人は「自分ならきっと提案をまとめられる」と感じ、積極的に準備を進めます。別の人は「どうせ自分には無理だ」と思って消極的になり、準備不足のまま失敗してしまう。違いを生むのは、能力そのものよりも「できると思えるかどうか」なのです。
この自己効力感が高い人は次のような特性を持ち、結果的に目標達成へ向かいやすくなります。
- 挑戦的な目標を設定する
- 困難に直面しても粘り強く努力する
- 失敗しても前向きに立ち直る
逆に自己効力感が低ければ、能力があっても「自分にはできない」と思い込み、行動できなくなってしまいます。
これは第5話で扱った エクスペクタンシー理論 の「努力の見通し(Expectancy)」と深く結びついています。
「努力すれば成果につながる」と頭で分かっていても、「自分にはできない」と思えば人は動きません。一方で「自分ならできる」と信じられれば、たとえ最初は低評価でも成果を出して周囲の評価を覆すことができるのです。
私自身、それまで「低評価」とされていた人が、自己効力感を取り戻すことで驚くほど良い仕事をしてくれる場面を何度も見てきました。
つまり、期待(エクスペクタンシー)と自己効力感は表裏一体なのです。
自己効力感を高める4つの方法
バンデューラは、自己効力感が以下の4つの要素から形成されると説明しました。これはマネジャーが現場でできる支援の指針にもなります。
1. 成功体験(Mastery Experiences)
小さな成功を積み重ねることが最も効果的です。いきなり大きな課題を与えるのではなく、達成可能なステップを用意し、「やってみたらできた」という経験をさせることが、何よりも自信につながります。
2. 代理経験(Vicarious Experiences)
自分と似た立場の人が成功する姿を見ることで、「自分にもできるかもしれない」と思えるようになります。若手同士で成功事例を共有させたり、少し先輩の挑戦を見せたりするのが効果的です。
3. 言語的説得(Verbal Persuasion)
リーダーからの「君ならできる」という言葉は大きな力を持ちます。ただし大切なのは、根拠のある言葉であること。「あなたが前回準備した提案、すごく分かりやすかった。今回も活かせるはずだ」と具体的に伝えることで、現実感のある励ましになります。
4. 生理的・情緒的状態(Physiological and Emotional States)
緊張や不安が強いと、「できない」と感じやすくなります。リーダーが安心できる環境を整え、失敗しても大丈夫だと伝えることで、心の負担を軽くしてあげることが重要です。

現場でどう活かすか
私が駆け出しの頃に感じた「隣に先輩がいてくれる安心感」は、まさに代理経験を自然に得られる機会でした。
今は誰もが最初から一人で現場に立たされる状況が増えています。だからこそ、次の工夫が必要です。
1. ペアリング制度を導入する
単独でタスクに取り組ませるのではなく、熟練者と初心者をセットにするペアリング制度は、自己効力感を高めるための優れた仕組みです。初心者は、隣にいる熟練者が困難な課題を解決する姿を間近で見ることができ、自分にもできるという代理経験を自然に得ることができます。
これには実は別の効果もあって、熟練者に新たな気づきを与える機会になったり、仕事や技術の承継など、トータルで見れば決して非効率ではないと思います。
2. 伴走型リーダーシップを実践する
ペアリング制度は非常に効果的ですが、「常に熟練者を新人に張り付けられるほど、人財に余裕がない」という企業も多いのが現実です。
そこで、より多くの組織で実践が期待されるのが、「伴走型リーダーシップ」です。部下を支えながらも、彼らの力を信じて見守るリーダーの存在は、どのような状況でも、メンバーの「自分はできる」という確信を強力に後押しします。
伴走型リーダーは、ヒントを与え、自力で解決するのを辛抱強く待ちます。これにより、部下は「自分の力でできた」という成功体験を得られ、自己効力感が飛躍的に向上します。
『伴走』の本当の意味
私が駆け出しの頃に感じた、隣に先輩がいる安心感。それは、伴走型リーダーシップが提供する「心の土台」そのものです。
現代の企業では、常に熟練者を新人に張り付けるのは難しいでしょう。そのときこそ、「伴走型リーダー」が求められます。部下にヒントを与え、辛抱強く自力で解決させることで、「自分でできた」という成功体験を積ませるのです。
伴走型リーダーとは、ただそばにいることではありません。
それは、部下が「自分ならできる」と信じられるように導き、自己効力感を育てることです。
その積み重ねが、個人の成長を加速させ、主体的に動く組織をつくり、幸せな会社づくりへとつながっていきます。
次回予告
次回は「成長的マインドセット(キャロル・ドゥエック)」を取り上げます。失敗や挑戦をどう捉えるかが、人の成長や自己効力感にどのように影響するのか、現場での活かし方も含めて掘り下げていきます。