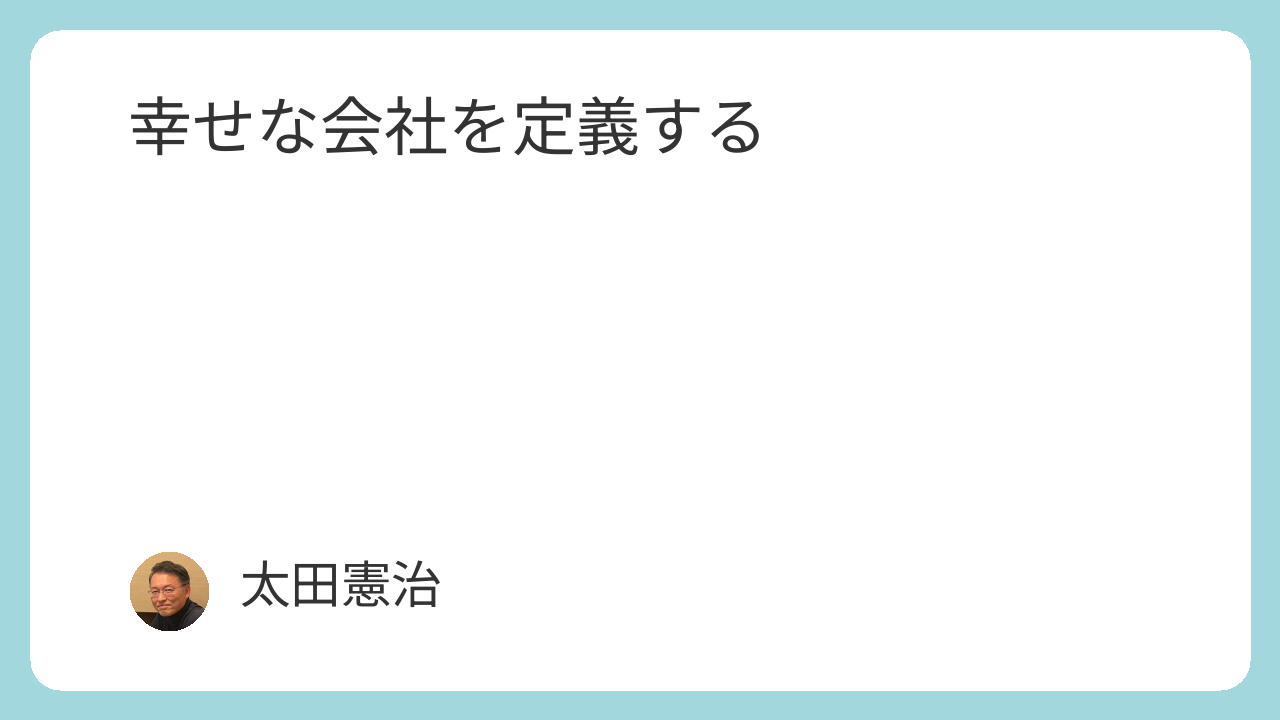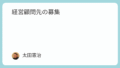幸福をテーマにするのはいいが
私は経営顧問として、その活動目的を「幸せな会社をつくること」としています。最近ではビジネス界でも「幸福」をテーマにすることへの違和感は少なくなってきているように思います。とは言え、幸福にも色々あって、新たな巨大市場としての幸福なのか、社員の幸福なのかで全く別の話になります。私が目的とするのは後者の社員の幸福のことですが、これも何が幸せかは人によって異なるので、利益を追求するのとは違って、数字で明確に測ることはできません。
もっとも、社員エンゲージメント調査の点数を経営のKPI(重要業績評価指標)とするなど、見える化に取り組んでいる会社も出てきているようではありますし、人事系コンサル会社に頼めば、あらゆる属性、階層毎に社員の満足度を数値化して分析してくれることでしょう。それらを活用するのは良いのですが、数字自体にどれほどの意味があるのかは疑問ですね。人の心を数字で捉えることへの限界もそうですし、実際にその数値の高い会社や組織を並べてみた時に、少なくとも私の経験上は違和感だらけでした。その違和感の正体をここで解説してもそれこそ意味がないのでやめておきますが。
マズローの欲求階層説を軸にする
では、そもそも幸福という人によって基準が違う、そんなフワッとしたようなものを目的にしていることが如何なものかという点に対して、私は以下のように考え方を整理しています。
アメリカの心理学者マズローの説として有名な「欲求の階層」をベースとしたときに、図のように「幸福の物質的基盤」と「つながりとしての幸福」と「自己実現としての幸福」という幸福の重層構造と重ね合わせることができます。そして、幸福が人によって多様であるというのは上層の部分を指しており、人間が生きていくのに不可欠のニーズに対応する幸福の物質的基盤は言わば幸福の土台にあたり、人にとって普遍的なものといえます。
そこで、私が実現したい幸せな会社とは、スローガン的に表現すると「ワクワクチームワーク」です。つまり1日の大半を過ごすであろう会社の存在が、「チームワーク」によるつながりを感じられるコミュニティとなっており、自己実現に向かって「ワクワク」できる状態です。それに対して、わたしの著書『銀行員を経営顧問にするという選択』でテーマとした「会社の永続性」とは「ワクワクチームワーク」を目指すにも会社の経営自体が安定していないとそれどころではないという意味で、幸福の物質的基盤に対する取り組みになります。
会社の永続性が第一である
私は別の記事で、会社にとって一番大事なこととは「永続性」であると述べました。それは、幸せな会社の土台とも言える「幸福の物質的な基盤」を固める意味でも第一であるということがお分かりいただけたでしょうか? そして、これはもう一つ重要な意味があります。
この幸福の物質的基盤に関しては、国家または社会的に保障されるセーフティネットが存在します。最近では世界的にベーシックインカムという概念も注目されていますが、常に問題となるのが財源です。特に我が国は。日本政府の借金は約1,300兆円、GDPの2倍以上という先進諸国の中でも突出した水準で、なお増え続けている状況です。これを国家破綻の危機と煽るつもりは無いのですが、持続可能性には疑義があります。そして政府はこれまでもこれからも経済成長がすべての問題を解決してくれるという御方便で先送りし、のみならず支持率を意識してかバラマキ的な政策を続けています。対抗する野党は、輪を掛けて減税をアピールしている状況において、財政はひたすら悪化していくと考えられます。民主主義国家において、その責任は有権者たる国民にあるというのが根の深い問題だと私は思ってしまいますが、嘆いていても仕方がありません。自分ができることを自分で考えて自ら行動するしかないのです。
つまり、私がやろうとしていることは、私たちの幸福を国家とか政治に委ねるのではなく、自分たちでコントロール可能なコミュニティである「会社」レベルで手を打とうということです。私たちの生活の基盤は、仕事に就いて給料をもらい生計を立てるということが基本になっており、社会的セーフティネットの根幹は雇用です。その意味で会社が永続的に雇用を生むことは、財政問題とは関係なく私たちの幸福の物質的基盤に貢献するのです。
ワクワクチームワークを実現するために
さて、私が第一の軸足としている”お金のスキル”によって会社の永続性を実現することは、先述した通り幸福な会社の土台となるものであり、かつ普遍的で、私の中でも考え方が固まっている部分です。故に著書としてまとめることもできたのですが、それだけではせいぜい「幸福の物質的基盤」を叶えることにしかなりません。
問題は、その先の「ワクワクチームワーク」を実現するために、いかにして「つながりとしての幸福」と「自己実現としての幸福」を叶えていくことができるかなのです。この点に関して、私が取り組んできたのは、第二の軸足である心理学的なアプローチによるマネジメントです。私は、これを”心のスキル”と呼びますが、これは決まった答えのない探究であり、ゴールのない挑戦になると思われます。
とは言え、私が試行錯誤してきたマネジメントの経験と、先人や現代の賢人たちの知恵と研究成果を重ね合わることで紐解けることがかなりあることも分かっています。そのあたりについて、今後このブログに綴っていこうかと思っています。